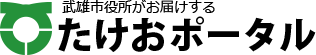国民健康保険税
国民健康保険税について
国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるよう、加入者が保険税を出し合い、お互いに助け合う制度です。国民健康保険制度の健全運営のため、みなさまのご理解ご協力をお願いします。
| 税率等の内容(令和7年4月1日以降) | ||
| 医療保険分(限度額66万円) | 所得割 | 10.22% |
| 均等割 | 23,300円 | |
| 平等割 | 33,800円 | |
| 後期高齢者支援金(限度額26万円) | 所得割 | 3.05% |
| 均等割 | 7,800円 | |
| 平等割 | 7,900円 | |
| 介護分(限度額17万円) | 所得割 | 2.36% |
| 均等割 | 9,500円 | |
| 平等割 | 6,700円 | |
- 医療保険分...医療費の支払いに充てる税額
- 後期高齢者支援金...後期高齢者医療制度に充てる税額
- 介護分...介護保険事業に充てる税額(40歳以上65歳未満の方にかかります)
- 所得割...世帯の総所得金額に応じて算定 ・均等割...被保険者一人あたりの税額
- 平等割...1世帯あたりの税額
~国民健康保険の健全な運営のためにも国民健康保険税は納期限内に納めましょう~
国保税の軽減
1.世帯の前年中の所得の合計(軽減判定所得)が定められた軽減基準額以下となる場合、均等割額・平等割額の軽減(7割軽減・5割軽減・2割軽減)を行っています。軽減基準額は下記のとおりです。(令和7年度から)
※なお、世帯の中に未申告の方がいる場合は軽減できませんので、収入がなかった場合も必ず申告をしてください。
- 「7割軽減」・・・43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数(注))-1)×10万円
- 「5割軽減」・・・43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数(注))-1)×10万円+(30.5万円)×被保険者数
- 「2割軽減」・・・43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数(注))-1)×10万円+(56万円×被保険者数)
(注)一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。
2.就学前の児童の均等割について5割を軽減します。(令和4年度から)
就学前の児童の均等割(医療保険分の均等割+後期高齢者支援金の均等割)の5割を軽減します。(上記1.で説明している軽減基準額に基づき7割軽減、5割軽減、2割軽減を行った世帯の就学前の児童については、それぞれの軽減後の均等割額の5割を軽減します。)
3.75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行されても、国保税の負担が制度移行前と同程度になるよう一定期間、軽減措置が設けられています。
- 国保の加入者が後期高齢者医療制度に移行し、国保の世帯員が減少した場合、後期高齢者へ移行した方の人数、所得も含めて軽減判定を行います。
- 国保の加入者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その世帯で残った国保加入者が1人になった場合、平等割額を最初の5年間2分の1減額する現行措置に加え、その後3年間は4分の1を減額した額になります。
- 会社の社会保険などに加入している被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、その方の被扶養者(65~74歳)が国保に加入する場合、所得割を0円、均等割を半額にします。また、旧被扶養者のみで構成される世帯については平等割も半額になります。なお、均等割・平等割については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までが軽減期間となります。
4.勤務先の倒産や解雇など自ら望まないかたちで離職した方(非自発的失業者)のうち、 65歳未満の雇用保険受給者については、申請によって離職日の翌日から最大2ヵ年度、前年の給与所得を30/100とみなして計算することで税額を軽減します。
(対象)以下の項目にすべて該当する方
- 平成21年3月31日以後に離職した方
- 離職時点で65歳未満の方
- 雇用保険受給資格者証の「理由」欄のコードが次のいずれかである方
11,12,21,22,23,31,32,33,34
※「雇用保険受給資格者証」の他に以下の受給資格者証がありますが、これをお持ちの方は軽減対象ではありませんのでご注意ください。
- 「特別受給資格者証」・・・季節的に雇用される又は短期の雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者の方へ交付されています。
- 「高年齢受給資格者証」・・・65歳到達日以後に離職された方へ交付されています。
国保税の減免
災害(震災、風水害、火災まど)やその他特別の事情などにより、生計を維持することが困難であると認められる場合、国保税の減免を受けることができる制度があります。
国保税の減免を受けようとする場合は、納期限前7日までに減免申請書(罹災証明書などの写し)を提出する必要があります。減免の対象となるのは、納期未到来分で未納付の国保税に限ります。遡っての減免は行いません。
お困りの際は、税務課までご相談ください。
国保税は世帯主が納税義務者です
国保税は世帯を単位とし、世帯主が納税義務者となります。世帯主が国保に加入されていない場合であっても、世帯の中に国保に加入している人がある場合、世帯主が納税義務者となります。
世帯主が後期高齢者医療制度の対象者である場合、国保税の計算の対象にはなりませんが、世帯の国保加入者の分については国保税を納めていただくことになります。この場合、後期高齢者医療保険料は年金から特別徴収されますが、国保税は普通徴収で納めていただきます。
お問い合わせ
制度について
福祉部 健康課 国保年金係
Tel:0954-27-7170
税に関して
総務部 税務課 市民税係
Tel:0954-23-9220