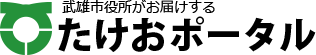市長提案事項説明要旨
おはようございます。
武雄市議会定例会の開会にあたり、一言ご挨拶申し上げます。

治水対策・防災についてであります。
全国各地で台風や線状降水帯の発生などによる自然災害が多発しており、事前の十分な備えや迅速な復旧対応が常に求められます。本市においても、先週、台風10号が接近した際には、市民への情報の周知や危険個所の点検、避難所の早期開設、備蓄の確認などを行い、万全を期して対応してまいりました。また、2年で2回の豪雨災害を経験し、大雨による災害を二度と起こさないため、治水対策にこれまで全力で取り組んでまいりました。
7月は何度も大雨に見舞われ、14日には時間雨量50ミリを越える非常に激しい雨が降ったものの、市内の浸水被害は、一部の田畑や道路の冠水にとどまりました。これは、河道掘削などによる川の流れの確保や高橋排水機場の増強といった排水能力の向上、ため池を活用した貯留量の増加など、昨今の治水対策の効果がみられたものと考えております。
また、北方町高野地区では、市建設業協会の方々により昨年度導入した排水ポンプ車を使った排水作業が行われました。さらに高野地区と久津具地区では、地域の方々の連携で水路を活用した排水対策が行われ、深刻な浸水被害を防ぐことができました。田んぼダムを含め、こういった流域治水の取り組みが着実に進んでいるのは、市民や関係者の皆さまのご協力によるものであり、心より感謝申し上げます。
現在、六角川の特定都市河川の指定を受け、関係機関とともに流域水害対策計画の策定を進めており、この計画の重点整備地区である朝日町、北方町、橘町において、治水とまちづくりについての住民意見交換会を継続して行っております。意見交換会では、地域で考える治水対策のアイデアやまちづくりに関する様々なご意見をいただいており、計画を策定する上での参考にさせていただきたいと考えております。
今後も引き続き、誰もが安心して暮らせるまちを目指し、計画策定にとどまらず様々な治水対策に全力で取り組んでまいります。
8月8日に発生した日向灘を震源とした地震では、宮崎県で震度6弱を観測したほか、市内でも最大震度2の揺れを観測しました。この地震を受け、気象庁は、南海トラフ地震の想定震源域で大規模地震が発生する可能性が高まっているとし「南海トラフ地震臨時情報」を発表しました。いつ起こるか想定できない災害に対しても、日頃からの十分な備えが重要であります。
6月には公益財団法人シビックフォースと共同備蓄に関する覚書を締結し、被災者へのきめ細かな支援につながるよう、母子避難を想定したパーテーションやおむつの交換台などの物資を災害時に連携して迅速に供給できる体制を整備しました。
昨日の市総合防災訓練では、大規模地震災害を想定した市民参加型の訓練を市民や消防団、関係団体などと連携し実施しました。
今後もあらゆる災害に備え、市民の防災意識、地域防災力の向上を図ってまいります。
大学誘致についてであります。
国の将来推計人口を基に分析された人口戦略会議の発表によると、現在4万7千人ほどの武雄市の人口は、2050年には3万7千人ほどに減少すると推測されています。地方創生が全国で叫ばれる中、人口減少を食い止め、持続可能で活気あるまちをつくることは喫緊の課題であります。
大学の誘致は、特に若者世代の人口減が激しい本市にとって、定住人口の増加につながるとともに、まちに大学があることで子どもが学べる機会が増え、加えて、学びたい人が、いくつになっても学べる場が増え、生きがいや夢をもつことにつながります。産業や地域も活性化し、豊かなまちの発展につながるものと確信しております。
これまで、大学設置に関する特別委員会等における議員の皆さまへの説明をはじめ、市民や高校生、各種団体の皆さまに、大学の基本構想や学びの内容、大学ができることによるまちへの効果等を学校法人旭学園と連携し積極的に説明を行い、ご意見を伺ってまいりました。そこでは、地域と共に学生を育てる大学の考えに共感するといった声や空き家の活用など地域でも協力できることがないだろうか、留学生にも安心して生活してもらうために、多文化共生への理解がもっと必要ではないかなど様々なご意見をいただいているところです。
6月の定例会では、旭学園に対する大学設置に関する支援予算に関し、議員の皆さまのご審議を賜りご承認いただきました。また、7月には県議会において、武雄アジア大学の設置に関する支援予算についてご承認いただいたところであります。
来月には、旭学園から文部科学省へ大学設置許可申請書類が提出される予定です。
大学ができることは、本市にとって大変大きなチャンスであります。今後も市民の皆さまへできるだけ多くの説明の場を設け、市民の皆さまからいただいたご意見は、旭学園とも共有するなど連携して、地域一体となって大学開学に向けて進めてまいります。
子育て・教育環境の充実についてであります。
時代の変化に対応する力が求められる今、学校教育においては、子どもたち一人一人に合わせた主体的な学びへの転換が求められています。これを踏まえ本市では、これまで全国に先駆けてICT教育や官民一体型学校などの取り組みを進めてきました。また、学校の教室には、不登校や発達障がい、貧困などの多様な支援が必要な子どもたちが同時に在籍しています。本市では、子ども一人一人に向き合うため、こどもの貧困対策や不登校対策、ヤングケアラー支援などに一早く取り組んできました。このような中、すべての子ども一人一人の特性を伸ばす取り組みをさらに進めるため、学校教育の方向性を示す「教育ビジョン」を策定します。このビジョンは、全市民へわかりやすく周知することで、学校や家庭だけでなく地域や企業も教育の当事者として、市全体で教育に対する理解を深めていただき、さらに一歩先の教育環境を目指してまいります。
また、通学路での交通事故を未然に防ぐため、車両の速度抑制効果があるハンプの設置やカラー舗装を新たに実施するとともに、改修が必要な区画線や防護柵の更新を行い、安全に通学できる環境を強化します。
築49年が経過する山内中央公園プールについては、全面改修を行います。屋外プールをはじめ、幼児用の小プール、その他新たにオフシーズンでも多様な利用ができる多目的スペースを整備します。家族で楽しく過ごせる場、地域住民同士が交流できる場としての活用を図り、もっと楽しく子育てができるまちを目指します。
生活環境の向上についてであります。
農業への支援は、食料の安定供給だけでなく地域の環境保全や市民の健康な生活の実現につながります。
6月に佐賀県で初めてジャンボタニシ注意報が発令され、市内でも平年の約3倍の数のジャンボタニシが発生し、苗や根の食害による収量や品質の低下など深刻な水稲被害が出ています。この大量発生の原因は、暖冬によって越冬した個体が増えたためと考えられており、被害の拡大を防ぐためには、正しい防除対策の普及や年間を通した対策が必要です。
農家やJAなどの関係機関と連携し、防除対策の理解を深めるための講習会を実施するとともに、受講者には石灰窒素の無料配布を行い、農家の負担軽減にもつなげてまいります。また、受講者にアンケートを実施し、今後のさらなる対策を関係機関と検討してまいります。これにより、農作物への被害を減らし、生産性や営農意欲の向上、安定した農業経営につなげてまいります。
また、築25年を迎え老朽化が進んでいる衛生処理センターについて、下水道浄化センターの隣接地を予定地として移設する基本計画を今年度末までに策定し、令和13年度の供用開始を目指します。市民の生活環境を維持し、あわせて効率的な汚水処理を実現すべく取り組んでまいります。
以上、市民の皆さまの命と暮らしを守ると共に、次の世代に続くまちをつくるための各種政策に全力で取り組んでまいりますので、議員各位のご理解・ご協力を切にお願い申し上げまして、私の提案事項説明とさせていただきます。
本議会もどうぞよろしくお願い申し上げます。